( ・ω・)世界終末ダイアリーその4 三なる箱庭世界
2022年3月31日 トリしばキューブ コメント (2)
終わらない歌を歌おう。
クソッタレの世界のため…。
・トリしば新カードプレビュー (233)
・トリしばキューブ (92)
・トリしば構築 (36)
合計記事数300超、
この日記においてかなりの割合を占めた
「トリしば」という名の、
MTGのオリジナルフォーマットについて書くゾ。
なんなら今朝も記事書いたばかりだけどw
MTGというカードゲームにおける、
遊び方の指針とでも言うべき「フォーマット」。
山ほどある印刷されたカードの中から、
どのカードが使えて、どのカードが使用禁止。
そういう定め、ルールというものには
公的なものと、そうでないものがある。
スタンダード。直近数年発売のカードセット収録のカードのみ、使用可能なフォーマット。
パイオニア、モダン。スタンの幅をn年広げたもの。
レガシー、ヴィンテージ。ほぼ何でもありって感じのもの。
いずれも公式に定められたフォーマット。
これらのフォーマット、つまり遊び方というのは、
実はかなり解りづらい事が問題ではないか、と思い始めたのは、
この記事で取り上げる「トリしば」を遊び始めてからになる。
何がどう分かりづらいのか?
たとえば《巨大化》という、昔からMTGにあるシンプルで有名かつ強力なカードがある。
一見すると、このカードがどのフォーマットで使用可能かどうかなんて、
簡単に分かりそうなものである。
パッと見で、そのカードのエキスパンションシンボルでわかるはずなのだから。
どのカードセットに収録されたものなのか、が。
しかし、MTGというゲームにおいては「再録」という、
昔登場したカードを、まったく同じ内容のまま再び印刷して再収録するという
ドケチな節約術 人気のカードをイラストなどだけ変更して再販するシステムがある。
そして再録されたカードというのは、たとえ印刷物が過去のそれであっても、
現行のカードセット(たとえば直近数か月に発売された最新作)に収録されていれば
大会などでも使用可能であり、パッと見では恐ろしく昔のカードであっても、
実は使用可能だったりする、という分かりづらさがある。
他にも、フォーマットごとに、カードセットという枠組みとは別に、
個別で「禁止カード」というものを名指しで設けている。
これに至っては、インターネット上に転がっている情報を見て
個々で識別するしかなく、知識のない人がカードだけ見ても、
そのカードが実際に使用可能かどうかは判別のしようがない。
たとえば《レンと6番》というカードは、スタンダードとパイオニアでは
カードセット自体が使用禁止のものにあたるのみならず、
レガシーにおいてはカードセット自体は使用可能であるにも関わらず
名指しで禁止指定を受けている。一方、モダンやヴィンテージでは使用可能だ。
この他にもややこしいカードはいくつもある。
そこで、オリジナルフォーマットの出番だ。
「トリしば」というフォーマットは、カードの右上に描かれた
マナシンボルのうち、色マナと呼ばれる数字やアルファベットではないマークが
3つ以上あるカードと、土地のみが使用可能、という
使用可能なカードに縛りを設けたものだ。
正確には、これに加えて「日本語版の印刷されていないカードも禁止」であるが。
(そして、現在はカードパワー的には問題無さそうだが、
過去の大会で暴れたことから《トレイリアのアカデミー》という土地カードも
一応禁止されてはいる……使えたとして使われるか怪しいが;)
このルールであれば、使用可能なカードというのは
文字通り「一目瞭然」なわけだ。
収録されたカードセットがいつの、どんなものだとか、
再録状況がどうだとか、公式の禁止指定リストなんかも存在しない。
「見ればわかる」という、その分かりやすさが良い。
しかしながら、対戦のゲームバランスははっきり言ってかなり悪い。
先行側が超が付くほど有利だし、使われるカードにしても
カードプール全体のうち、ほんの数パーセントしか採用されない。
カードパワーの高さに対して初期ライフが20と、通常のルールと比べて
相対的に低くなっているがゆえ、決着も一瞬でついてしまう。
せっかくの、使用可能なカードの分かりやすさだとか、
豪快なカードパワーを味わえるダイナミック感も、
これでは味わいきれない。
物凄く上手い料理なのに、一瞬で皿から消えてしまうのだ。
これはもどかしい。もっと味わいたい! そう思うのは当然の事。
なので、このトリしばで使用可能なカードをだいたい1枚ずつ集め、
600枚揃えたキューブを作ってみた。
https://mtg-jp.com/reading/kochima/0018194/
これが「トリしばキューブ」。
長く、長く手をかけて作り続けている、この日記のコンテンツの1つだ。
通常のMTGのルールとは別に初期ライフを30にしたり、
いきなり基本土地が2枚戦場に出ている状態でゲームを始められたりなど、
独自のルールも採用しつつ、凄まじい色拘束と高いパワーを誇るカード群で
ハチャメチャなゲームが楽しめる。
そんなトリしばキューブも、作成してからもう8年近くになる。
色々なカードが投入され、あるいはバランスの問題もあって抜けていったが。
来月発売される「ニューカペナの街角」では、
トリしばで使用可能なカードが多く新登場する見込みだ。
土地カードを除いても最低15枚はほぼ確定。
20枚以上、あるいは30枚以上になる可能性も十分にある。
それは間違いなく嬉しい事であり……。
しかし、トリしばキューブのゲームバランスの事を考えれば、
何かしらの調整が必要になることも明らかである。
特定の色の組み合わせのカードばかりが割合を増してしまうと、
その組み合わせでデッキを組む戦略ばかりが有利になってしまい、
そうでない色の組み合わせのカードが使われにくくなる。
それではキューブを制作するにあたっての、
「色んなカードを味わってほしい」という指針がブレてしまうのだ。
この日記サイトがサービス終了して以降も、
トリしばキューブとの格闘は続いていく。
長らくその記録を書きとどめてきたサイトが閉鎖するにあたって、
今書くべきは、今後のトリしばキューブに関する長期的な展望だ。
「トリしばで使える、色んなカードを味わってほしい」という指針。
これに反するのではないか? ということで、
残念ながら以下のカード達はキューブから外してきた経緯がある。
①強すぎるカード
②弱すぎるカード
③色拘束が厳しすぎるカード
①は、たとえばそのカードを唱えたら、ほぼ勝利が確定してしまうようなカード。
そのカード1枚でほとんど勝ててしまうため、
せっかくピックした他のカードの出番が無くなるし、
対戦相手からも、そうしたカード達を使用する機会を奪ってしまう。
強い事は問題ないが、強すぎる事は問題なのだ。
②は、①とは逆に、全く使えたものではないカード。
たとえば、唱えて戦場に出したものの、何もできないカードとか。
コストが重すぎて唱える機会がそもそもやってこないカードとか。
環境の問題も大きい。環境に合わないものは、楽しめないということ。
寒い冬には美味しい鍋焼きうどんも、暑い夏には食えたものではない。
美味しくいただけないのは環境のせい。別の環境で、食べてもらうほかない。
③については、②にも通ずるもので、
そもそも唱えるのが難しいのだから、弱いよね、というお話。
しかし実はそれだけではなく……これこそが、未来の展望のお話。
現在のトリしばキューブでは、単色のカードは基本的に色マナがちょうど3つの
カードしか採用されていないものの、
混色のカードにおいてはその限りではない。
たとえば4色や5色のカードが10枚ずつ、計20枚近く採用されている。
https://ishikobafuji.diarynote.jp/202106231136318344/
これ自体は、ゲームバランスにおいて問題ない事を
テストプレイにて何度も確認している。
トリしばキューブでは4色の色マナ基盤を揃えることは容易であり、
5色デッキの構築すらも非常に簡単だ。
ゆえに、4色や5色のカードは、弱すぎるカードとしては
採用を見送ったり、新カードと入れ替えたりする理由たりえない。
問題視しているのはそこではなく……。
公式フォーマットと非公式(=トリしば)との比較で前述した、
「見た目においての分かりやすさ」の部分にある。
いや、あるいは見た目ではなく、「聞こえ」と言うべきか…?
「トリしば」という、構築/リミテッドの別なき括りについて。
より詳しく言えば、そのフォーマットの命名に関してのお話。
このフォーマットの発案者はKawasaki氏。
https://zkawasaki.diarynote.jp/
偉大なるプレインズウォーカーがつけたこのフォーマット名は、
呼びやすいように省略されたものであり。
省かずに呼ぶと、「トリプルシンボルしばり」という名称のはずだ。
(あくまでも推測でしかないが。)
しかし、ここで1つ問題がある。
「トリプルシンボル」というのは、MTGにおいては
色マナが3つあるカード……という意味ではない。
正しくは、「単一の色マナが3つであるカード」なのだ。
http://mtgwiki.com/wiki/%E3%83%88%E3%83%AA%E3%83%97%E3%83%AB%E3%82%B7%E3%83%B3%E3%83%9C%E3%83%AB
この事は多くのMTGプレイヤーが周知するところであり、
3色や5色のカードが使用できてしまう、トリしばのフォーマットとしての
ルーリングとは矛盾している命名であると言える。
もちろん、
「実はトリプルシンボルじゃあなくって、
Triple Colored(有色)Symbol の略だ」という考え方も出来る。
が、そうだとしても、
「じゃあちょうど3つの物しか使用不可なんじゃないの?
4つ以上の有色シンボルを持つカードはダメなんじゃないの?」
という疑問は残る。
これへの抜け道もまた、「トリプル or more ~ の略だよ」とか
いくらでも考えようはあるし、
そもそもそうしたカードが使える事に異を唱えようという気はないのだ。
トリしばというフォーマットの発案者はmigiTではないのだし、
今更キューブから、そうしたカードを取り除けるのか?
という事情も、長らくあった。
……そう、長らくはあったのだが。
先ほども述べた通り、カードは増え、
そして更にまた来月に増えようとしている。
キューブの総カード枚数には、限りがある。
デジタルデータではなく実物で遊ぶ以上は、持ち運ばなければならないが、
その枚数が多ければ多いほど、負担は大きくなるし。
ゲームバランス的にも、割合を調整する必要があるというのは前述の通りだ。
そしてそうなると、外すカードを考える必要も出てきて。
かつては埒外としてきた、「色マナが4つ以上ある」というだけでの
不採用理由も、現実的な理由へと近づいてくる。
このボーダーをすぐに設けるつもりはない。
なぜならば「分割カード」という、現状のトリしばキューブにおいて
ゲームバランスを、或いはゲームの楽しさを支えるカード種の多くを
外すことへと繋がってしまうからだ。
ゲームとしてのMTGには、コンバットトリックや除去といったスパイスが
その楽しさを増すために必要不可欠だ。
プレイタイミングの豊富さ、対象という選択肢。
それに加えて、トリしばキューブでは軽さや色拘束もプレイングのバリエーションを豊かにしてくれる。
しかし現状のトリしばキューブにおいて、そんな分割カードの多くは
色マナシンボルの合計数が4つ以上であるものが大半を占める。
それらをすべて除外するというのはバランス調整上、非常に厳しい。
なのでこの調整案、キューブの新たな採用/不採用方針は、
当面の間は見送るべき、しかしいずれは考えるべき、
まさに「長期的な展望」ということだ。
さて、Diarynoteに書き込めなくなる明日にも、
また新しいニューカペナのストーリーが来る。
そして、新しい3色カードも公開されるだろう。
それに関してmigiTもまた、別のブログにて感想などを書くつもりだ。
終末を迎えて以降も、トリしばは、トリしばキューブは続いていく。
その果てを、未来を見たい人たちよ。
終末の向こうで、また会おう!
( ・ω・)ノシ
クソッタレの世界のため…。
・トリしば新カードプレビュー (233)
・トリしばキューブ (92)
・トリしば構築 (36)
合計記事数300超、
この日記においてかなりの割合を占めた
「トリしば」という名の、
MTGのオリジナルフォーマットについて書くゾ。
なんなら今朝も記事書いたばかりだけどw
MTGというカードゲームにおける、
遊び方の指針とでも言うべき「フォーマット」。
山ほどある印刷されたカードの中から、
どのカードが使えて、どのカードが使用禁止。
そういう定め、ルールというものには
公的なものと、そうでないものがある。
スタンダード。直近数年発売のカードセット収録のカードのみ、使用可能なフォーマット。
パイオニア、モダン。スタンの幅をn年広げたもの。
レガシー、ヴィンテージ。ほぼ何でもありって感じのもの。
いずれも公式に定められたフォーマット。
これらのフォーマット、つまり遊び方というのは、
実はかなり解りづらい事が問題ではないか、と思い始めたのは、
この記事で取り上げる「トリしば」を遊び始めてからになる。
何がどう分かりづらいのか?
たとえば《巨大化》という、昔からMTGにあるシンプルで有名かつ強力なカードがある。
一見すると、このカードがどのフォーマットで使用可能かどうかなんて、
簡単に分かりそうなものである。
パッと見で、そのカードのエキスパンションシンボルでわかるはずなのだから。
どのカードセットに収録されたものなのか、が。
しかし、MTGというゲームにおいては「再録」という、
昔登場したカードを、まったく同じ内容のまま再び印刷して再収録するという
そして再録されたカードというのは、たとえ印刷物が過去のそれであっても、
現行のカードセット(たとえば直近数か月に発売された最新作)に収録されていれば
大会などでも使用可能であり、パッと見では恐ろしく昔のカードであっても、
実は使用可能だったりする、という分かりづらさがある。
他にも、フォーマットごとに、カードセットという枠組みとは別に、
個別で「禁止カード」というものを名指しで設けている。
これに至っては、インターネット上に転がっている情報を見て
個々で識別するしかなく、知識のない人がカードだけ見ても、
そのカードが実際に使用可能かどうかは判別のしようがない。
たとえば《レンと6番》というカードは、スタンダードとパイオニアでは
カードセット自体が使用禁止のものにあたるのみならず、
レガシーにおいてはカードセット自体は使用可能であるにも関わらず
名指しで禁止指定を受けている。一方、モダンやヴィンテージでは使用可能だ。
この他にもややこしいカードはいくつもある。
そこで、オリジナルフォーマットの出番だ。
「トリしば」というフォーマットは、カードの右上に描かれた
マナシンボルのうち、色マナと呼ばれる数字やアルファベットではないマークが
3つ以上あるカードと、土地のみが使用可能、という
使用可能なカードに縛りを設けたものだ。
正確には、これに加えて「日本語版の印刷されていないカードも禁止」であるが。
(そして、現在はカードパワー的には問題無さそうだが、
過去の大会で暴れたことから《トレイリアのアカデミー》という土地カードも
一応禁止されてはいる……使えたとして使われるか怪しいが;)
このルールであれば、使用可能なカードというのは
文字通り「一目瞭然」なわけだ。
収録されたカードセットがいつの、どんなものだとか、
再録状況がどうだとか、公式の禁止指定リストなんかも存在しない。
「見ればわかる」という、その分かりやすさが良い。
しかしながら、対戦のゲームバランスははっきり言ってかなり悪い。
先行側が超が付くほど有利だし、使われるカードにしても
カードプール全体のうち、ほんの数パーセントしか採用されない。
カードパワーの高さに対して初期ライフが20と、通常のルールと比べて
相対的に低くなっているがゆえ、決着も一瞬でついてしまう。
せっかくの、使用可能なカードの分かりやすさだとか、
豪快なカードパワーを味わえるダイナミック感も、
これでは味わいきれない。
物凄く上手い料理なのに、一瞬で皿から消えてしまうのだ。
これはもどかしい。もっと味わいたい! そう思うのは当然の事。
なので、このトリしばで使用可能なカードをだいたい1枚ずつ集め、
600枚揃えたキューブを作ってみた。
https://mtg-jp.com/reading/kochima/0018194/
これが「トリしばキューブ」。
長く、長く手をかけて作り続けている、この日記のコンテンツの1つだ。
通常のMTGのルールとは別に初期ライフを30にしたり、
いきなり基本土地が2枚戦場に出ている状態でゲームを始められたりなど、
独自のルールも採用しつつ、凄まじい色拘束と高いパワーを誇るカード群で
ハチャメチャなゲームが楽しめる。
そんなトリしばキューブも、作成してからもう8年近くになる。
色々なカードが投入され、あるいはバランスの問題もあって抜けていったが。
来月発売される「ニューカペナの街角」では、
トリしばで使用可能なカードが多く新登場する見込みだ。
土地カードを除いても最低15枚はほぼ確定。
20枚以上、あるいは30枚以上になる可能性も十分にある。
それは間違いなく嬉しい事であり……。
しかし、トリしばキューブのゲームバランスの事を考えれば、
何かしらの調整が必要になることも明らかである。
特定の色の組み合わせのカードばかりが割合を増してしまうと、
その組み合わせでデッキを組む戦略ばかりが有利になってしまい、
そうでない色の組み合わせのカードが使われにくくなる。
それではキューブを制作するにあたっての、
「色んなカードを味わってほしい」という指針がブレてしまうのだ。
この日記サイトがサービス終了して以降も、
トリしばキューブとの格闘は続いていく。
長らくその記録を書きとどめてきたサイトが閉鎖するにあたって、
今書くべきは、今後のトリしばキューブに関する長期的な展望だ。
「トリしばで使える、色んなカードを味わってほしい」という指針。
これに反するのではないか? ということで、
残念ながら以下のカード達はキューブから外してきた経緯がある。
①強すぎるカード
②弱すぎるカード
③色拘束が厳しすぎるカード
①は、たとえばそのカードを唱えたら、ほぼ勝利が確定してしまうようなカード。
そのカード1枚でほとんど勝ててしまうため、
せっかくピックした他のカードの出番が無くなるし、
対戦相手からも、そうしたカード達を使用する機会を奪ってしまう。
強い事は問題ないが、強すぎる事は問題なのだ。
②は、①とは逆に、全く使えたものではないカード。
たとえば、唱えて戦場に出したものの、何もできないカードとか。
コストが重すぎて唱える機会がそもそもやってこないカードとか。
環境の問題も大きい。環境に合わないものは、楽しめないということ。
寒い冬には美味しい鍋焼きうどんも、暑い夏には食えたものではない。
美味しくいただけないのは環境のせい。別の環境で、食べてもらうほかない。
③については、②にも通ずるもので、
そもそも唱えるのが難しいのだから、弱いよね、というお話。
しかし実はそれだけではなく……これこそが、未来の展望のお話。
現在のトリしばキューブでは、単色のカードは基本的に色マナがちょうど3つの
カードしか採用されていないものの、
混色のカードにおいてはその限りではない。
たとえば4色や5色のカードが10枚ずつ、計20枚近く採用されている。
https://ishikobafuji.diarynote.jp/202106231136318344/
これ自体は、ゲームバランスにおいて問題ない事を
テストプレイにて何度も確認している。
トリしばキューブでは4色の色マナ基盤を揃えることは容易であり、
5色デッキの構築すらも非常に簡単だ。
ゆえに、4色や5色のカードは、弱すぎるカードとしては
採用を見送ったり、新カードと入れ替えたりする理由たりえない。
問題視しているのはそこではなく……。
公式フォーマットと非公式(=トリしば)との比較で前述した、
「見た目においての分かりやすさ」の部分にある。
いや、あるいは見た目ではなく、「聞こえ」と言うべきか…?
「トリしば」という、構築/リミテッドの別なき括りについて。
より詳しく言えば、そのフォーマットの命名に関してのお話。
このフォーマットの発案者はKawasaki氏。
https://zkawasaki.diarynote.jp/
偉大なるプレインズウォーカーがつけたこのフォーマット名は、
呼びやすいように省略されたものであり。
省かずに呼ぶと、「トリプルシンボルしばり」という名称のはずだ。
(あくまでも推測でしかないが。)
しかし、ここで1つ問題がある。
「トリプルシンボル」というのは、MTGにおいては
色マナが3つあるカード……という意味ではない。
正しくは、「単一の色マナが3つであるカード」なのだ。
http://mtgwiki.com/wiki/%E3%83%88%E3%83%AA%E3%83%97%E3%83%AB%E3%82%B7%E3%83%B3%E3%83%9C%E3%83%AB
この事は多くのMTGプレイヤーが周知するところであり、
3色や5色のカードが使用できてしまう、トリしばのフォーマットとしての
ルーリングとは矛盾している命名であると言える。
もちろん、
「実はトリプルシンボルじゃあなくって、
Triple Colored(有色)Symbol の略だ」という考え方も出来る。
が、そうだとしても、
「じゃあちょうど3つの物しか使用不可なんじゃないの?
4つ以上の有色シンボルを持つカードはダメなんじゃないの?」
という疑問は残る。
これへの抜け道もまた、「トリプル or more ~ の略だよ」とか
いくらでも考えようはあるし、
そもそもそうしたカードが使える事に異を唱えようという気はないのだ。
トリしばというフォーマットの発案者はmigiTではないのだし、
今更キューブから、そうしたカードを取り除けるのか?
という事情も、長らくあった。
……そう、長らくはあったのだが。
先ほども述べた通り、カードは増え、
そして更にまた来月に増えようとしている。
キューブの総カード枚数には、限りがある。
デジタルデータではなく実物で遊ぶ以上は、持ち運ばなければならないが、
その枚数が多ければ多いほど、負担は大きくなるし。
ゲームバランス的にも、割合を調整する必要があるというのは前述の通りだ。
そしてそうなると、外すカードを考える必要も出てきて。
かつては埒外としてきた、「色マナが4つ以上ある」というだけでの
不採用理由も、現実的な理由へと近づいてくる。
このボーダーをすぐに設けるつもりはない。
なぜならば「分割カード」という、現状のトリしばキューブにおいて
ゲームバランスを、或いはゲームの楽しさを支えるカード種の多くを
外すことへと繋がってしまうからだ。
ゲームとしてのMTGには、コンバットトリックや除去といったスパイスが
その楽しさを増すために必要不可欠だ。
プレイタイミングの豊富さ、対象という選択肢。
それに加えて、トリしばキューブでは軽さや色拘束もプレイングのバリエーションを豊かにしてくれる。
しかし現状のトリしばキューブにおいて、そんな分割カードの多くは
色マナシンボルの合計数が4つ以上であるものが大半を占める。
それらをすべて除外するというのはバランス調整上、非常に厳しい。
なのでこの調整案、キューブの新たな採用/不採用方針は、
当面の間は見送るべき、しかしいずれは考えるべき、
まさに「長期的な展望」ということだ。
さて、Diarynoteに書き込めなくなる明日にも、
また新しいニューカペナのストーリーが来る。
そして、新しい3色カードも公開されるだろう。
それに関してmigiTもまた、別のブログにて感想などを書くつもりだ。
終末を迎えて以降も、トリしばは、トリしばキューブは続いていく。
その果てを、未来を見たい人たちよ。
終末の向こうで、また会おう!
( ・ω・)ノシ
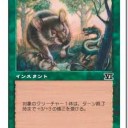



コメント
進化させていく心意気。
素晴らしい。
終末のその先でもより良い未来がありますように。
オリジナルフォーマット、もっと言えばMTGの購入者が
そのそれぞれで遊び方を考えるというのは、
実は公式にとっても有益なことなんですよね。
実際、近年においても「ブースター探偵」だとかいった遊び方を
提示していたりしますし。
製品を買って以後は、それぞれが、そのカードを用いて好きに遊べる。
それもまたMTGの魅力の1つということですね。
( ^ω^)